
がなされている点は、大いに参考にすべきであると考える。これらの港湾整備は、個々の港の港勢を急速に拡大しようとするのではなく、現在の施設のあい路を絶ち、老朽施設を思い切ってスクラップし、最新の施設に更新するものである。日本では、20年前に一担実行したことであるが、欧州ではまさしくいま行なわれている。このことが、市場の活性化を促している原動力だと感じた。 このたびの調査で、欧州におけるリストラが順調に進んでいることを実感した。リストラといっても、これまで抱えていた技術分野のすべてを切り捨てると言うのではなく、自らの最も得意とする部門を尊重し、もっぱらその分野の技術開発を促進する反面、その他の分野に関わるものを思い切って切り捨てたところが注目に値する。IHC系列に入ったものの、相変わらず浚渫船の専業メーカーとして、一層発展し、市場拡大を達成したGUSTO社などはその模範であると考える。 1月の訪問の時にロンドンからの帰路、臨席のアンドリューという若いイギリス人の株式アナリストは、日本の株式市場は非常に難しい曲面にあると困惑していた。かれは、日興證券UKの社員で、英国で日本株式を販売するのである。1週間の滞在で、数社を訪問し、経営状態などを分析して帰るのであるが、彼の目には日本市場は決して魅力的には写ってはいないようであった。 日本は、どうしてこうなってしまったのだろうか。一時期、日本はもはや先進国の中で最も経済力が豊かであると自認し、ふくれ上がった黒字減らしのために、海外商品の購入が奨励され、海外への旅行者が急増した。かつては、お金もなかったが、よしんばお金があったとしても、物がないので、ほしいものがあっても絵に擶いた餅であった。それが、経済成長に伴い、給与水準が上がり、しかも、為替レートが高騰したため、一方では生産業が瀕死の状態であるにも拘らず、海外の有名ブランド商品が手軽に入手できるようになった。とくに、戦後二世の若者は、両親や祖父母が彼等と同じ年代に経た艱難辛苦を知らず、気楽に高級ブランド品などを志向する。惰報メディアの発展は、筆記をも忘れさせる。目標を持って、努力して、勝ち得ようと 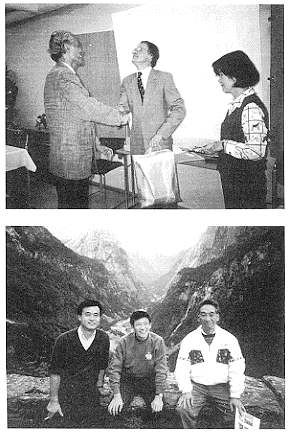
前ページ 目次へ 次ページ
|

|